2025年10月21日、マジック:ザ・ギャザリング公式が
統率者戦フォーマットにおける「ブラケット制度」のベータ版をアップデートしました!
今回の更新は以下の内容が中心となっています。
- ブラケットの定義の明確化
- 主要な3つのルールの変更
- ゲームチェンジャーリストの大幅な調整
この記事では、ブラケット制度のアップデート内容を整理したいと思います。
引用元は次の公式アナウンスの二つですが、WeeklyMTGの内容が分かりやすく意図が明確だったため、
そちらを中心にまとめています。
↓はWeeklyMTGの動画です。
↓はMTG公式のブラケット・アップデートの記事です。
アップデート内容のまとめ
ルール・ゼロの重要性
ブラケット制度の「真の目的」
統率者戦をプレイする中で
「せっかくテーブルについたのになんだかデッキのパワーレベルが全然合わない」
という悩ましい問題。
そこで登場するのが公式が導入したブラケットシステムになります。
リードデザイナーのGavin Verheyさんは、
このブラケットシステムの「真の目的」は至ってシンプルだと言います。
それは、
「プレイヤーにゲームを始める前に会話をしてもらうためのうまいきっかけを作ること」です。
ブラケット毎の勝敗ターン数の基準の明確化
今回のアップデートで最も大きな変更点は、各ブラケットが目指す方向を示す新しい基準ができたことです。それがこの「想定ターン数の導入」です。
これまでは「序盤のコンボはなしで」といった曖昧なルールが存在し、人によって解釈が異なり混乱の元となっていました。
そうした多くの意見を受け、
各ブラケットで「誰かが勝敗を決するまでに予想されるターン数」に関する具体的な指針が導入されました。
ここで言うターン数とは、
「プレイヤー全員が満足してゲーム体験ができる時間」という考え方となります。
つまり8ターン内でゲームを終わらせるという意味ではなく、
8ターンの間は楽しくプレイできるくらいを目指しましょう、という考え方ですね。

例えば3~4ターンで実質的に負けている状況なのに、無意味に引き延ばされても楽しくないですよね
| ブラケット | 期待されるターン数 | 想定されるゲームプレイ |
| ブラケット 1 (Exhibition) | 勝利または敗北が始まる前に、プレイヤー全員が少なくとも9ターンはプレイできることが期待されます。 | 勝利よりも、テーマやユニークな発想、創造性を見せ合うことに重点が置かれます。 |
| ブラケット 2 (Core) | 勝利または敗北が始まる前に、プレイヤー全員が少なくとも8ターンはプレイできることが期待されます。 | デッキは非最適化で素直なものが期待され、昔ながらの古き良き統率者戦を楽しむレベルです。 |
| ブラケット 3 (Upgraded) | 勝利または敗北が始まる前に、プレイヤー全員が少なくとも6ターンはプレイできることが期待されます。 | 強力なシナジーやエキサイティングな妨害が飛び交い、7ターン目以降はいつゲームが終わってもおかしくないレベルです。 |
| ブラケット 4 (Optimized) | 勝利または敗北が始まる前に、プレイヤー全員が少なくとも4ターンはプレイできることが期待されます。 | cEDHのメタゲームとは異なりますが、できる限り早く、そして安定して勝つことを目指した超高速デッキの戦場です。 |
| ブラケット 5 (cEDH) | ゲームはいつでも終了する可能性があります。 | 勝利を最優先し、競技レベルのメタゲームで戦うために緻密に設計されたデッキが集まる場所です。 |
これは厳格なルールではなく、そのブラケットで期待されるゲームプレイの方向性を示すものです。
ゲームの展開によっては、
想定されるターン数よりも早く特定のプレイヤーが敗北するケースも許容されることに注意が必要です。
ブラケット定義における3つの主要な変更点
ブラケット1(Exhibition) のテーマ性強化
ブラケット 1は、パワーよりも目標、テーマ、アイデアを優先するデッキのための場所として、
その位置づけが強化されました。
このレベルでは、ルール・ゼロの重要性が特に強調されており、
例えば、テーマに合致するならば、本来ルール上不許可であるはずのゲームチェンジャーの使用も、
対戦相手との話し合いによって容認されるべきだとされています。
(例:ニコル・ボーラスをテーマにしたデッキにおける《ボーラスの城塞》)
ブラケット2から「構築済み統率者デッキ」の記述の削除
以前、ブラケット 2 (Core) は「構築済み統率者デッキ」と関連付けられていましたが、
この関連が切り離されました。
理由は次のとおりです。
- 「構築済み統率者デッキ」のパワーレベルは(モダンホライゾン3の「構築済み統率者デッキ」とスターター「構築済み統率者デッキ」など)大きく異なり、一律に定義することが困難であるため
- 過去に「構築済み統率者デッキ」に意図せずゲームチェンジャーや無限コンボが含まれてしまった事例があったため、誤ったメッセージを送らないようにするため
「サーチカードの使用制限」の廃止
デッキビルダーにとって朗報なのが、これまで曖昧だった「サーチカードは少数でお願いします」というルールが、全てのブラケットから撤廃されたことです。
今後は、本当に強力で効率の良いサーチカードは、ゲームチェンジャーリストの方で管理されることになります。
これにより、効率の悪い高マナのチューターを多数採用することに対する懸念が解消されます
「ゲームチェンジャー」リストの見直し
今回の更新で、合計10枚のカードがゲームチェンジャーリストから削除されました。
今後は、ゲームを早期(ターン 2または 3)に急速に歪める低マナ域のカードに焦点を当てるため、マナ総量の高い(7、8、9マナの)強力なカードはリストから外す方針が明確化されました。
8ターン目で強力な呪文が唱えられるのは、統率者戦の性質上受け入れられやすいとされています。
ゲームチェンジャーリストから除外されたカード:高マナ域(4枚)
《召し上げ》のような高マナのカードは、そもそも唱えること自体がゲームのクライマックスのようなものであり、リストで注意喚起する必要はないと判断されました。
ゲームチェンジャーリストから除外されたカード:統率者(4枚)
《最高工匠、ウルザ》のような統率者は、ゲームが始まる前から誰が使うか分かっているため、対戦相手と事前に話し合えば対応できるという考え方に変わりました。
また、これらのカードをデッキの99枚の中に入れたいプレイヤーの機会を奪わないという意図もあります。
ゲームチェンジャーリストから除外されたその他のカード(2枚)
ゲームチェンジャーリストに残る注目カード(今後の検討対象)
以下の3枚のカードは、リストに残されていますが、将来的に削除される候補としてコミュニティからのフィードバックが求められています。
コミュニティフィードバックを求める4つの議論のトピック
現時点ではルール変更は行われていませんが、統率者戦の将来に大きな影響を与える可能性のある以下の4つのトピックについて、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはコミュニティからの広範な意見を求めています。
リスティックの研究は禁止すべきか?
このフォーマットを象徴するカードでありながら、一方的にゲームを支配する力も持っています。
カジュアルなプレイヤーたちが本当にこのカードがある環境を楽しめているのか、意見が求められています。
タッサの神託者は禁止すべきか?
《Demonic Consultation》や《汚れた契約》と組み合わせた、cEDHにおける主要な勝利条件になっています。
cEDHコミュニティ内でも意見が分かれているため、フィードバックが歓迎されています。
また、ブラケット 3やブラケット 4のような、よりカジュアルなゲームで
この2枚コンボがどれほど抑圧的であるかについての情報を特に求められています。
デッキ構築時の混成マナのルールを変更すべきか?
混成マナの扱いに関する議論です。
デッキ構築の目的でのみ、混成マナ(例:白/緑)を(白または緑)として扱うことができるようにする。
もし変更されれば、《台所の嫌がらせ屋》のようなカードが単色のデッキでも使えるようになり、デッキ構築の幅が大きく広がる可能性があります。
カードのテキストボックス内に特定のマナシンボルを持つカード(例:《死儀礼のシャーマン》の黒マナシンボル)は、引き続きその色のアイデンティティを定義し、このルールの対象外となります。
統率者戦に6番目のブラケットは必要か?
現在のブラケット2と3の間、あるいは3と4の間に追加すべきかどうかが議論されています。より細かくレベル分けしてほしいという声に開発チームは耳を傾けています。
ブラケット 3 と 4 の間
無制限のゲームチェンジャーを使いたいが、最適化されたデッキ(ブラケット 4)のような速さ(クイックコンボ)を求めないプレイヤー向け。
ブラケット 2 と 3 の間
ゲームチェンジャーは使わずに、ブラケット 2よりも若干高いパワーレベルでプレイしたいプレイヤー向け。
最後に
以上、統率者戦における「ブラケット制度」のアップデート情報まとめでした。
個人的には良いアップデート内容で、
統率者が快適に遊びやすくなるのではないかなと感じました。
みなさんもご意見があれば是非コメントを頂ければと思います。
(こちらのX(旧Twitter)で情報発信をしています)
本記事の画像や情報は、マジック:ザ・ギャザリング公式よりファンコンテンツポリシーに沿って引用しているものも含まれています。
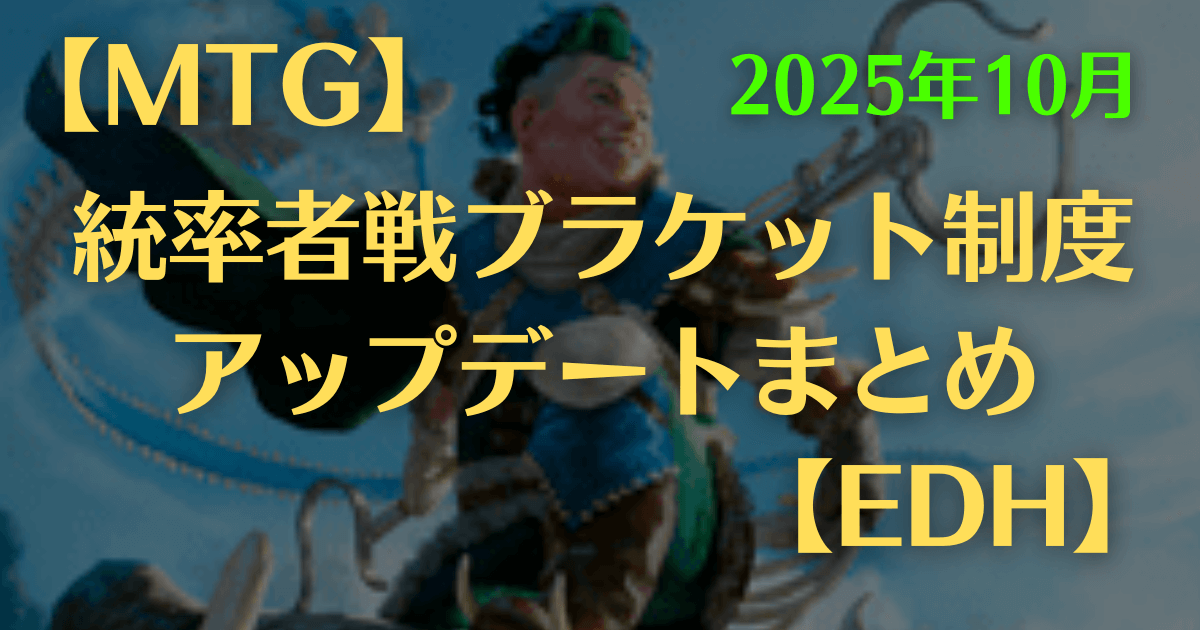


















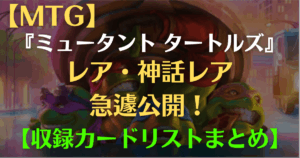
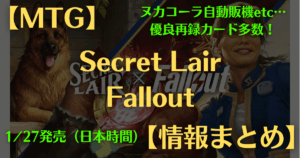
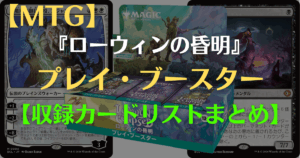
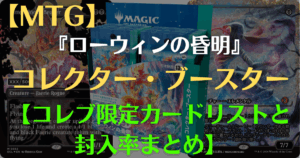
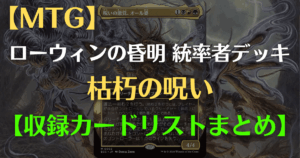
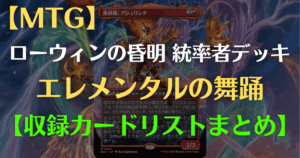

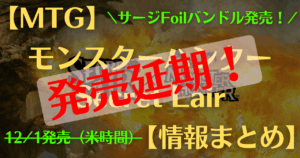
コメント